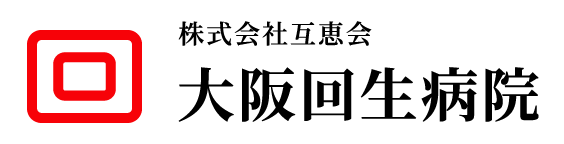糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は糖尿病により網膜に障害が生じる疾患です。
3つのステージに分類されます。
いずれのステージにおいても黄斑部(ものを見る中心部分)に浮腫が生じる可能性があり、それに対する治療としてステロイドや抗VEGF薬の注射などもあり、外来にて治療を行っております。
単純網膜症
網膜に点状出血を生じます。
この時点では自覚症状はあまりありません。
治療は血糖コントロールが中心となります。
前増殖網膜症
糖尿病により網膜の血流が悪くなり、無潅流領域と呼ばれる血流不良の場所がでてきます。
蛍光眼底造影検査などで詳細を把握します。
無潅流領域が多数あると、新生血管と呼ばれる脆い血管ができ、硝子体出血などを引き起こす可能性があり、無潅流領域が広い場合には網膜光凝固(レーザー治療)を行います。
硝子体出血などを生じた場合には硝子体手術を行うこともあります。
増殖網膜症
前増殖網膜症から進行し、網膜の上に増殖膜と呼ばれる膜を認めます。
膜が増加してくると網膜剥離を引き起こすこともあります。
この段階では硝子体手術により膜を除去します。
網膜静脈閉塞症
網膜静脈閉塞症は網膜の静脈が血栓などにより閉塞し、出血する疾患です。
黄斑部に浮腫が生じる場合(黄斑浮腫)があり、その場合視力が低下することがあります。
黄斑浮腫の治療としてステロイドや抗VEGF薬の注射などがあります。
また、血流の不良の場所に網膜光凝固(レーザー治療)を行うこともあります。
硝子体出血を起こした場合には硝子体手術を行うこともあります。
加齢黄斑変性症
黄斑部の下に新生血管が生じ、出血や浮腫、網膜剥離などを生じることで視力が低下したり、ものが歪んで見えたりする疾患です。
治療は長期にわたることが多いですが、抗VEGF薬の注射などによっていい状態を維持できるよう、治療を行います。
裂孔原性網膜剥離
眼球には中心部分に硝子体というゲルが存在し、年齢の変化などで収縮してきます。
この際、網膜に弱い部分があったりすると硝子体の収縮する力により牽引され、網膜に穴(裂孔)が生じることがあります。
網膜裂孔に対しては光凝固(レーザー治療)による治療を行います。
しかし、時間がたつと裂孔から硝子体液が網膜の下に回り込み、網膜が浮き上がってしまいます。
これを網膜剥離といいますが、この状態になれば手術療法による治療を行います。
網膜に穴が開いてしまった場合、飛蚊症(虫が飛んでいるような黒い点がみえる)が生じたり、網膜剥離にまで進展した場合には視力が低下したり、視野が障害されたりします。
手術には眼の外から行う方法(網膜復位術)と中から行う方法(硝子体手術)がありますが、網膜剥離の状態などにより総合的に判断し、よりよい方法を選択させていただいております。
手術の過程で眼の中にガスを注入することもあり、その場合は術後下向きの姿勢をしていただくことにより網膜をもとに戻すということもあります。
黄斑円孔
裂孔原性網膜剥離が生じる機序と同様、硝子体の牽引にて黄斑部に穴が開いてしまった状態をいいます。
歪みや真ん中が見にくいといった症状がでてきます。
いちど穴が開いてしまえば自然閉鎖することは少ないため、これも手術(硝子体手術)による穴の閉鎖を行います。
この手術でも術後は眼内にガスが入るため、下向きの姿勢を維持していただく必要があります。
黄斑上膜(網膜前膜)
硝子体が収縮したあと、一部の硝子体が網膜側に残された状態になったものをいいます。
あまり膜が強くない場合は無症状で経過観察のみでいいこともありますが、歪みや視力低下などを生じた場合には硝子体手術による膜の除去が必要となることもあります。
硝子体手術について
上記に挙げた疾患に対する手術として硝子体手術があります。
疾患によりさまざまですが、おおよそ1.5時間~3時間の手術で、通常は局所麻酔にて行います。
硝子体を切除することにより、硝子体の牽引を除去し、眼内の環境を変化させることで疾患の改善を目指します。
手術は3~5か所の小さい穴を眼にあけて行います。
硝子体を処理した後、各疾患に応じた処理を行います。
当院では高速回転により安全性の向上した機械を用いて手術を行っております。
場合により眼内にガスを注入して手術を終了することもあり、その場合はうつむきの姿勢などを要することもあります。
術後合併症として出血、細菌感染などが挙げられ(数千人~一万人にひとり程度)、慎重な経過観察を要するため当院では入院での手術を施行しております。
詳細につきましては主治医とご相談ください。