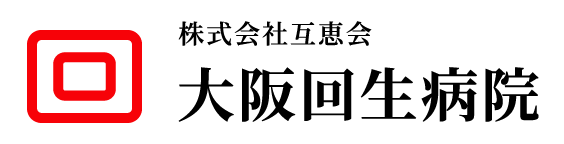正常圧水頭症は高齢者に生じる慢性の水頭症(脳の中の髄液が増加する病気)であり、認知機能障害や歩行障害、排尿障害といった症状がおこります。
高齢人口の約1%に生じると報告されており、決して稀な疾患ではありません。
一方で、正常圧水頭症の診療に専門性高く取り組んでいる脳神経外科施設はそう多くはありません。
私たちは正常圧水頭症を正確に診断し治療方針を提案するために、同疾患についてだけでなくアルツハイマー病などの変性認知症についても幅広い知識をもって診療にあたっています。
正常圧水頭症は、正確な診断と適切な治療を受けることにより劇的に症状が改善します。
高齢を理由に日常生活の質をあきらめる前に、一度ご相談いただけたら幸いです。
他院でシャント手術を受けた方もご相談ください
正常圧水頭症の治療はシャント手術を受けても終わりではありません。
症状や日常生活の状況に合わせて適切なシャント圧設定を行い、頭部CTやMRIを撮影して脳に異常がないことを定期的に確認する必要があります。
これらの目的で、私の外来ではシャント術を受けた患者様には半年に一回のペースで来院いただくようにしております。
他の病院で既に手術を受けられた患者様で、転居などの理由から手術を受けた病院への通院が途絶えている方なども積極的に受け入れております。
前医からの紹介状を持参いただく方が望ましいですが、むつかしければ直接受診いただいても結構です。
患者と家族の体験談|高齢者の水頭症 iNPH.jp